|
���j������ �o�T�i�T�C�g�Љ�j�Fhttp://blog.goo.ne.jp/mugi411/e/4ce781667167c84b5eba820e4c6fa7ef �g�[�L���O�E�}�C�m���e�B�@�]�@�Ǐ��A���j�A�f��̘b����ɏ����Ԃ�d�q���z �����Ƌ��Y��`�i2008-08-2721:26:18|���j�����z�j �@���Y��`�Ƃ����Βj���������f���A�����d����v�z�Ƃ̃C���[�W���������B�l�b�g�����B��������́A���̎��Ԃ�����ƒm����悤�ɂȂ��Ă������A'80�N��ł��j�������Љ�̍s���n���������⋌�\�A�ɓ������{�̏��͓��قł͂Ȃ������B�����}���N�X���̂͒j�������ȂǁA�ꌾ�������ĂȂ������̂��B�w�l���L�����F����Ǝ��锭�������Ă���B �@�w���Y�}�錾�x(��g����)��2�͂̈ꕔ�������u���O�L��������B�}���N�X�̔���ɂ܂�Ȃ��v�w�ς��m��āA���ɋ����[���B �@�����ċ��Y��`�҂�A�N�����͕w�l�̋��L���̗p���悤�Ƃ���̂��낤�A�ƑS�u���W���A�K���͈�Ăɉ�X�Ɍ������ċ��ԁB�u���W���A�ɂƂ��ẮA���̍Ȃ͒P�Ȃ鐶�Y�p��Ɍ�����B�����琶�Y�p��͋����ɗ��p������ׂ��ł���A�ƕ����Ɣނ�͓��R�A���L�̉^�������l�ɕw�l���������ł��낤�Ƃ����l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�����Ŗ��ɂ��Ă���̂́A�P�Ȃ鐶�Y�p��Ƃ��Ă̕w�l�̒n�ʂ̔p�~���A�Ƃ������Ƃɂ̓u���W���A�͎v��������Ȃ��B�����Ă����Y��`�҂̂�������F�̕w�l���L�ɋ��������킪�u���W���A�̓����ƂԂ�قǏ��ׂ����̂͂܂��ƂȂ��B���Y��`�҂͕w�l�̋��L��V���Ɏ������K�v�͂Ȃ��B����͂قƂ�Ǐ�ɑ��݂��Ă����̂��B �@�킪�u���W���A�͔ނ�̃v�����^���A�̍Ȃ►�����R�ɂ��邾���ł͖������Ȃ��B�����ɂ��Ă͘_�O�Ƃ��Ă��A�ނ�͎��������̍Ȃ��݂��ɗU�f���āA����������̊�тƂ��Ă���B �@�u���W���A�̌����͎��ۂɂ͍Ȃ̋��L�ł���B���Y��`�҂ɔ�����������Ƃ���A���������ŋ��Y��`�҂͋U�P�I�ɓ����ɂ����w�l�̋��L�̑���ɁA���F�́A���R����w�l�̋��L��������悤�Ƃ���Ƃ������炢�ł��낤�B���Â�ɂ���A���݂̐��Y���W�̔p�~�ƂƂ��ɁA���̊W���琶����w�l�̋��L���܂��������F����є���F�̔������܂����ł��邱�Ƃ͎����ł���c �@�w�l�̋��L�������o�����̂́A���͋ߑ㋤�Y��`�҂ł͂Ȃ��B����5���I���̃T�[�T�[�����y���V�A�ɒa�������}�Y�_�N���̊J�c�́A���Y��w�l�̋��L������Ă���B�}���N�X���}�Y�_�N��m���Ă����̂��s�������A�}�Y�_�N���k�̍s�������n���Y��`�^���Ƃ�����R���ł���B�Љ���v�^���ł������͎̂��������A�y���V�A�Љ�卬���Ɋׂ邱�ƂɂȂ����B �@�Ȃ����I�Ȑ��Y�p��Ƃ��Ă����u���W���A�ƈႢ�A���Y��`�҂͂���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��Ɛ錾����B������19���I�Ƃ����A�w�l�́u���Y�p��v�Ƃ����\���̓L�c���B�����͎Y�ދ@�B�Ɠ������x���ł���B �@�}���N�X�̓u���W�������u���������̍Ȃ��݂��ɗU�f�A����������̊�тƂ��Ă���v�ƌ����B�s�ς͉����̎�������������A���l�̍ȂɎ���o���Ă��A�Ȃ̍Ȃɓ������Ƃ������t�シ��̂��w�ǂ̒j�ł͂Ȃ����B����̓u���W���������łȂ����w�K���ɂ��Z���F�l�̍ȂƖ��ʂ���҂������B���͎҂��͂Ƀ��m�����킹�A�g���̉��̎҂̍Ȃ►�����R�ɂ����̂͋��Y��`�����ς��Ȃ��B����F�̔����������Ă����B����͑̐������������̏������߂�Y�̖{�\�������ł���B �@���[�j���͉ƒ�ɓ���Ǝ���q��Ăɐ�O���鏗��Y�I�ƌ��Ȃ��A�Ɠ��z��ƕ\�������B���̗}����Ԃɂ��鏗���������𐄐i����B�������ă\�A�ŏ��͉Ɠ��z��ł͂Ȃ��Ȃ�A�J���҂Ƃ������̉ƊO�z��ƕϖe����B�鐭����ł͐��Y�p��̑��݂������̂��A�����w�I�ɐ��Y�̑��A�J���p��̖����������B�P�Ȃ鐶�Y�p��Ƃ��Ă̕w�l�̒n�ʂ̔p�~�̌��ʂ������B�ё����ɂ��d�����̘J�����ۂ��B�u�����͒j���Ɠ��������̓��̘J�����o����B�Y�O�Y��ɓ��̘J�����o���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��v�Ƃ̖т̌��t���w�}�I�x�㊪�ɂ���B �@��������A�����̒n�ʌ���Ƃ����A���Ȃ蕷�����͂悢�B�����A���Ԃ͓`���I�ȉƒ�̔ے�Ɣj�����B���\�A����A�����ƍ��O�������������Ƃ����B�D�u�Ǝd�������鋤�Y�}���������̎p�̓��f�B�A�f���������A�v���p�K���_�̑��ʂ��������B �@�����A���Ă̎��{��`�����A���[�L���O�E�[�}�������V�������̐������Ƃ��茖�`���镗���ł́A��Ȃ��Ƃɋ��Y��`���Ǝ��Ă���B������͔w��ɂ���͎̂��{�Ƃł���A�����J���͊m�ۂ̂��ߏ��̎Љ�i�o�͖]�܂������ƂȂ̂��B���͑����Ì�����������g���ہA�������Ӑ}������̂͑̐����Ⴆ�ǂ��������낤�B�������A���Y��`�Ǝ��{��`�̌���I�ȈႢ�͌�҂��Ȃ�Ȃ�Ƃ����_�A�v�z�̎��R�̕ۏႳ��Ă���_�ɂ���B ���֘A�L��:�u���E���̋��Y��`�^���v �c�c�c�c�c�c�� �o�T�i�T�C�g�Љ�j�Fhttp://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/3867/page031.html ���t�F�~�j�Y���ƃ}���N�X��`�@-�@�t�F�~�j�Y���ɐ��ވ������w�i �@���߂Ďw�E����܂ł��Ȃ����Ƃ����A�t�F�~�j�Y���̍����͋��Y��`�i�}���N�X�E���[�j����`�j�ɂ����B �� �@������A�����܂ł͂�����x�m�F���悤�Ǝv���̂����A���̑O�Ƀt�F�~�j�Y���̗��j��U��Ԃ��Ă݂悤�B�}�g�勳���̒��씪�m���́w������~���ێ�̓N�w�x�ŁA�u�t�F�~�j�Y���̃C�f�I���M�[�́A�O���ɂ킯��̂��֗��ł���v�Əq�ׂĂ���B �@�����́A�P�X���I����Q�O���I���ɂ����Ă̕w�l�Q�����Ȃǂ́u�j�������v�v�z�@-�@�����u���x�����E�t�F�~�j�Y���v�ł���B �@�����́A�w�V���������̑z���x�̃x�e�B�E�t���[�_����ɂ���čL�߂�ꂽ�u���f�B�J���E�t�F�~�j�Y���v�ł���B����́u�j�������i�}���E�w�C�e�B���O�j�v�u�j���Ɉ�����鏗���ւ̎��f�v����Ƃ���t�F�~�j�Y���ł���B�}���N�X��`�͂��̑����Ɍp�����ꂽ�B���̎咣�ɂ́A�@�I�A���I�Ȑ��x�����ɗ��܂�Ȃ����Ƃɂ܂Ŗ��ɂ��Ă���B�܂�����ߎq���ɑ�\�����u�}���N�X��`�t�F�~�j�Y���v���A���̕��h�ƌ�����B �@��O���́A�u�W�F���_�[�v���J�����A���̍\���̉�̂�ڎw�����̂ł���B�u�W�F���_�[�t���[�v���������Ă��鍡�̓��{�ł���B �� �@�t�F�~�j�Y���Ƃ́A���Y��`�̎v�z���Ɉʒu�t������B��ԕ�����₷���̂��A�}���N�X��`�̊K�������j�ςɒj���Ă͂߂邱�Ƃł���B �@�܂�A�j�����u���W���A�ɁA�������v�����^���A�[�g�ɁA�Ƃ�����ł���i���邢�́A�W�F���_�[���x�z�\���ƕ߂炦�邱�ƂȂǁj�B �@�\�\���Y��`�Ƃ��ė͂��������}���N�X��`�����������`�Ŏc���Ă���̂��B�u���҂Ǝ�ҁv�u�x�z�҂Ɣ�x�z�ҁv�u���͎҂Ɣ팠�͎ҁv�u�x�T�w�ƕn���w�v�c�c�B �@�܂��A�}���N�X�Ƌ��Ƀ}���N�X��`�C�f�I���M�[�����グ���t���[�h���b�q�E�G���Q���X�̒����w�Ƒ��E���L���Y�E���Ƃ̋N���x���t�F�~�j�Y���ɂ͑傫�ȉe����^���Ă���B �@����́A�u�v�͉Ƒ��̒��Ńu���W���A�ł���A�Ȃ̓v�����^���A�[�g���\����v�Ƃ����u�K���j�ρv�ɂ��O����A���ꂪ���̃t�F�~�j�Y���́u�Ƒ���́v�^���̊�Ղł���B �@�����Ƃ��G���Q���X���w�C�M���X�ɂ�����J���ҊK���̏�ԁx�ŁA�Ȃ������ɏo�邱�Ƃ́u�ƒ��S�ʓI�ɕ�����͕̂K�R�ł���v�A�ƒ낪���邱�Ƃ́u�v�w�ɂƂ��Ă��q���ɂƂ��Ă�����������Ƃ��������ʂ������炷�v�ƔF�߂Ă���̂ł��邪�B �@�܂�A���ǂ́A�u�ƒ�v�Ƃ����u�v���u���W���A�@�ȁ��v�����^���A�[�g�v�̍\�}����E���A���̂��߂Ɂu�Ƒ��i�ƒ�j�v�����i��́j������A�Ƃ�����Ȃ̂ł���B �@�}���N�X�͂��̎咘�w���{�_�x�̒��ł��������Ă���B �u���{��`���x�̓����ɂ�����Â��Ƒ����x�̉�̂��A�����ɋ��낵���ĉ}�킵�����̂Ɍ����悤�Ƃ��A����ɂ�������炸�A��H�Ƃ́A�Ǝ��̗̈�̔ޕ��ɂ���Љ�I�ɑg�D���ꂽ���Y�ߒ��ɂ����āA�w�l�A�j���̎Ⴂ�҂Ǝ����Ɍ���I�Ȗ��������Ă邱���ɂ���āA�Ƒ��Ɨ����W�Ƃ̂�荂�x�Ȍ`�Ԃ̂��߂ɐV�����o�ϓI��b��n�o����v �@�������}���N�X�������u���x�Ȍ`�ԁv�Ƃ́A���_�A�Љ��`���i�Љ�j�̂����ł���B �� �@���؏G������o�ϑ叕�����́A�w�N�������łڂ������x�̒��Ńt�F�~�j�Y�����ڎw���A���ɂ̃��[�g�s�A�\�\�u�t�@�����X�e�[���v�ƌĂ�鋤���̂��Љ�J���g���𖾂炩�ɂ��Ă���B �@����́u��z�I�Љ��`�ҁv�t�����\���E�}���[�E�t�[���G�i�W�F���_�[�t���[�̔����ҁj���咣�������̂ŁA���̎��Ԃ́A��v��w���͖��Ӗ��ƂȂ�A�����⌋���͏]���̍S���������������A�����̎��R������A�v�w���u�Q�g�A�R�g�A���邢�͂S�g�v�Ō��ۂ��邱�Ƃ��\�ɂȂ�B����ɉƑ����p�~�����̂ŁA�����A�玙�����O���������B�u�X�J�[�g�ƃY�{���Ƃ����ΏƓI�Ȉߕ��Œj������ʂ��邱�Ɓv����������\�\���������Љ�ł���B �@�t�F�~�j�Y���̖��Ƃ�����̂���������ɂ́u�Љ��`�v���v�����L�蓾�Ȃ��̂ł���B �@�\�\�t�F�~�j�X�g���Ȃ��u�V���O���}�U�[�v�𐄏����A��Ǝ�w�����ʂ��A�Ƒ����������邩�B�܂�́A���̔w�i�Ƀ}���N�X��`�������Ă̂��ƂȂ̂��B �@���m�̂Ƃ���A���Y��`�i�}���N�X�E���[�j����`�j�͏I�������B�x�������̕ǂ͕��ꂽ���A�\�A�����ł����B �@�����A���{�ł͎��͂��̋��Y��`�����ԂƂ��ɐ����c��A����A�����A���_�E�ȂǁA������Ƃ���ɖ������A�����ĉe���͂��������Ă���̂��B �� �@�_���؋��B���Y��`���A�܂��t�F�~�j�Y�����ڎw���u�Ƒ���́v���A���j�ɂ���Ă��̔s�k���ؖ����ꂽ�B �@�\�r�G�g���{�́u��������v�����s���悤�Ƃ����B�Ƒ�����̂����悤�Ƃ��A����܂ł̂��Ƃ���A�H���A�����A���������Ɉڍs���邱�Ƃɂ��A�u�ƒ�̕��S�v���珗�����u����v���邱�Ƃɂ����B �@�����A����͎��s�ɏI���B �u�C�M���X�̘J���҂̎S��Ɠ������J��L�����v�āA����Ɂu���N�̐�������Ƒ������Ɋւ��鍬���������v�A�������������u�o���������������v�B�܂��u���N�ƍ߁E��s���}���v���A�u��A���̑����Ɋւ����ᔻ�v�����܂�A�u�ނ�͋ΘJ�҂̏Z���ɐN�����A���D������j���肵�āA��R�҂͎E�C�����v�B �@���̎��R���Ə����̉���́A���̖ړI�Ƃ͗����Ɂu���҂Ɨ��\�҂����ʂƂ��ď����邱�ƂɂȂ�A��҂Ɠ��C�Ȏ҂�ɂ߂��邱�ƂƂȂ����v�B �@���̂悤�ȎU�X�Ȍ��ʂɁA�P�X�R�S�N�A�\�r�G�g���{�͉Ƒ�����я���������������A�Ƒ��̋������������̂ł������B�i�w���u�l���v�錾�x�j �@���ꂾ���łȂ��A���݂̃X�E�F�[�f���ł�������A�P�X�U�O�`�V�O�N��ɃE�[�}�����u�̗��������r�ꂽ�A�����J�̏A�w�������k�̂قڂT�O�����Аe�Ƃ�����O�̍��������Љ���сi�I�j������̂��B �� �@���Y��`�i�}���N�X��`�E���[�j���j�̓����ł���A���낵���Ƃ���́A���ꂪ�}���N�X��`�I�ȍl���ł���A�C�f�I���M�[�ł���Ƃ������ƂɋC�t�����ɁA���̊Ԃɂ�����Ă��܂����Ƃɂ���B �@�Ƃ���ŁA�{���ɋ��Y��`�͏������~���A�u�}���v��u���ʁv����������̂��낤���H �@�ʂ����ă��[�j���i�X�^�[�����j������\�A�͏���������������H �@�����͏�����������ꂽ�̂��H �@����A���������u�t�F�~�j�Y���v�u�W�F���_�[�t���[�v�͏������~���̂��H�@�������̂��H �@���͎v���\�\���������Ղȁu���z�v�قǁA���낵�����̂͂Ȃ��A�ƁB �@�t�F�~�j�Y���̔��z�̕����A�}���N�X��`�B�c�c�ɒ[�ɕ����A�ƒ�̕v�w�W�A��ʂ̒j���Ԃ̊W���A�͊W�A�㉺�W�Ƃ��đ�����\���c�c�B �@����Ȃ��̂��������������Ƃ́A�ƂĂ�����Ȃ����M���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �� �@�m�[�x�����w��҂ł���o�[�g�����h�E���b�Z���͎��̂悤�ɎЉ��`�i���Y��`�j���w�E���Ă���B �u�c�c�{���V�F���B�Y���́A����ɂЂƂ̐������_�ł��邾���ł͂Ȃ��B��������k�ȋ��`�Ɨ슴�̂��������o�T��������ЂƂ̏@���ł����v�\�\�ƁB �i�Q�l�����j �@���؏G���w�N�������łڂ������x �@���؏G���w���u�l���v�錾�x �@���씪�m�A�n������w������~���@�ێ�̓N�w�x �@�ɓ����Y�w�j���w����x �@�ѓ��`�w�t�F�~�j�Y���̊Q�Łx �c�c�c�c�c�c�� �o�T�i�T�C�g�Љ�j�Fhttp://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_he/a6fhe805.html �����{�l�Ɏӂ肽���`���郆�_�����V�̜����i���j�` �������_�����V�����������a���̌������� ��������T�́F���Y��`�̓��_���l������� �������{���Y�}����Ă��͉̂�X�̍ő�̌�肾���� �@���_���l�����{�l�Ɏӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ő�̖��́A�����{���Y�}����Ďc�u���҂Ƃ��Ďc���Ă��������Ƃł���B����͋�̓I�ɂ̓j���[�f�B�[���[���S�čs�Ȃ������Ƃł���B���Y��`�ҌQ���琬���Ă����j���[�f�B�[���[�͎Љ��`�v�������s�Ȃ�Ȃ��������A��O�̓��{�ɂ������ނ��H�Ȓ��������ׂĔj���̂ł���B����ȏ�ɑ傫�Ȍ��́A�c�u���҂Ƃ��ē��{���Y�}����āA�c�������Ƃł���B �@��X�������v�ɂ���ĔƂ��������A���̎c�u���ҁ����{���Y�}�Ȃ��肹�A�����Ƃ����Ɍ����ȓ��{�l�͖{���̓��{�����ɑh�������ł��낤�B�����ٔ��A���{�����@�A���̑��̐����v�ɂ�鈫�����A���̕a�����^�u�[�ɂ��Ĉ�w���ɐG�ꂳ�����Ƃ�����{���Y�}�Ȃ��肹�A�Ƃ����ɕ��@���ꂽ�ł��낤�B �@�����ٔ��̏ꍇ�́A����Ƀj���[�f�B�[���[���������_������O����̓��{���Y�}�̍u���h�j�ςƈ�v���邱�Ƃɂ����{���Y�}���Ƃ炦���̂ł��邪�A���{�����@�̏ꍇ�́A���ȏ��I�}���N�X�E���[�j����`�����m��Ȃ����{���Y�}�𑨂���ׂ��v�f�͂قƂ�ǂȂ��B����Ƃ���A��Q�W���̋ΘJ�҂̒c�����̕ۏႮ�炢�̂��̂ł���B���Ƃ͂��ׂă}���N�X�E���[�j����`�̋��ȏ�����͏o�Ă��Ȃ����̂ł���B �� �@�ł͉��̂ɁA����ɂ�������炸���{���Y�}�͂���قǂ܂łɓ��{�����@��M������̂��A�s�v�c�Ɏv����ł��낤�B �@���̓����̓��_�����̏@���I�����͂Ȃ̂ł���B�����Ȃ肱�������Ă����{�̊F�l�ɂ̓s���Ƃ��Ȃ����낤�Ƃ������Ƃ͎��ɂ��悭������B �@���≽�����A���{���Y�}���g���S���ӎ����Ă��Ȃ��B��ʂ̐����v�A�Ⴆ���ƈӎ��A�����ӎ��̋����ɂ��Ă��A�ʂ����ē��{���Y�}���ǂ̒��x���̈Ӗ���m���Ă��邾�낤���B���炭�A�v�����^���A���ێ�`�Ƃ������ȏ��ɂ�������炱����l���Ă���̂ł��낤�B����������ł́A�킩���Ă���Ƃ͂�����B�}���N�X��`�̍��Ƙ_�܂ł���܂��܂��ł��낤�B�܂�A���Ƃ�j��ɂ͈����S�̔@�����̂��ő�̏�Q���ɂȂ�킯�ł���B�������{���Y�}�����̕ӂ܂ŕ������Ă����Ƃ����Ȃ�A���͂ǂ����낤�B�Ƒ����x�͍��Ɠ]���̂�͂�傫�ȏ�Q���Ȃ̂ł���B���@�ɂ��鎩�R�A�����A�j���������͂��ׂĂ��̖ړI�ɓY�������̂ł��邪�A���{���Y�}�͂����܂Œm���Ă��ē��{�����@�����炵�Ă���̂��낤���B���ɂ͂����͎v���Ȃ��B �@�Ƃ���A���{���Y�}�����{�����@�������^�u�[�Ƃ��Ď��炷�鍪���́A�}���N�X�E���[�j����`����͓����o���Ȃ����낤�B�ł͂���͂ǂ�������������̂��B����̓��_�����̎����͂Ƃ��������ł��Ȃ��悤�ł���B�[���@�����Ƃ�������̂ł���B �q�����r �����}���N�X��`�́u���_����������v�̂��߂̋��\���_������ �@���̓��{�̍����ɍő�̐ӔC������̂̓}���N�X��`�ł���B �@�}���N�X��`�̊Q�łƂ������ꍇ�A���ʂ͕\�ʂɌ���ꂽ���́A�Ⴆ�Έ��ۑ����̔@�����̂Ƃ����������A���{���Y�}�̖���A�����{�j�̂����āA�v���Ƃ����}���N�X��`�̌����I���Ђ͂Ȃ��Ȃ����ƍl���邩���m��Ȃ��B�����A���͂���Ȑ��Ղ������̂ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂́A�}���N�X��`�Ƃ͒P�Ȃ�u�v�����_�v�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �@�}���N�X��`�̐��ɂ�����e���̍ł�����̂́A���̍e�łƂ�グ����̕a���A���ϐ��A���{���j�̐^�̍\�z��j����s��������o�����Ƃ������Ƃɂ���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B �@��������̓I�ɂ����ƁA���ƁE�����ӎ��A�����S�̋����A�����ς̎��āA�q����`�̔|�{�A�Ƒ����x�̕���A���̑��A��O�̓��{�����E�Ɍւ������₵�����������Ă����߂����Ƃɂ��낤�B�}���N�X��`�͂��̕a���̐��_�I�x���ƂȂ��Ă���̂ł���B����͍����̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B���̂Ȃ�A���{���Y�}�͐�O�̓��{�̒��������ׂāu��Έ��v�Ƃ��Ĕے肷����̂ł���B�����āA���{���Y�}�̓}���N�X��`��B���̐��E�ςƂ��ĐM�鐭�}�ł���B �@���̕a���̂��ׂĂ��}���N�X��`�Ɩ��ڂȊW�����邱�Ƃ͂킩�������A�����͂����P�ɎU�݂��Ă��������ł͂���قǂ̉e�����y�ڂ������ǂ����^�킵���B����ɂ͂�͂肱�����ЂƂ܂Ƃ߂Ƀp�b�N���āA���������{�����ɋ�������͂����������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A�����J��̌R���̃j���[�f�B�[���h�ł���A���̏��Y�ł�����{�����@�Ƃ��̗i��҂Ƃ��Ă̓��{���Y�}�Ȃ̂ł���B �����}���N�X��`�����ߒ��̎햾���� �@���āA����قǂ܂łɑ���̉e��������{�ɋy�ڂ����}���N�X��`�Ƃ͈�́A�@���Ȃ���̂Ȃ̂��B �@���{�݂̂Ȃ���́A���\�_���Ƃ������̂�M�����邾�낤���B����͈ꌩ�w��̌n�̔@���̍ق𐮂��Ă��邪�A�����͐^���Ԃȋ��\�_���ł���Ƃ������̂ł���B���E�ɂ́A��ώ�̍����\�_���Ƃ������̂����݂���̂ł���B���ꂪ�}���N�X��`�Ȃ̂ł���B �@�����������݂�ݒ肷��ɂ́A�Q�̑O�v�������ł��낤�B�P�͈�̒N���A�����P�͉��̖ړI�ł���Ȃ��̂��\�z�����̂��B���̂Q�̑O��ɓ����Ȃ���A���̂悤�ȉ��݂͎����o���Ȃ��ł��낤�B������ɂ���̓��́A���ɂ��킹��A�����Ԃ�ȒP�ɏo����̂ł���B���_�����������Ȃ̉�����Ƃ̂��߂ɁA�Ƃ����̂����̓��ł���B �@�����A���炭���{�͐��E�ň�Ԃ��̂��Ƃ𗝉����ɂ������ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ����̂́A���{�͐��E�ō������̃}���N�X��`�������ւ��Ă��鍑������ł���B����͋t���ł���B��O�̓��{���{��`�_���̔@�����̂͑��̍��ɂ͂Ȃ��B�u���{�_�v�̌��������{�����E��ł��낤�B�܂苕�\�_����^���Ɗ����������Ă���ł��鍑�����{�ł���Ƃ������Ƃł���B����͓��{�Ƀ��_����肪���݂��Ȃ��Ƃ������ƂƂ��W������B �@�ł͉��̃��_�����������\�_�����\�z�������ɂ��ďq�ׂ悤�B���_�������̋ꂵ���߂������Q�̗��j�ɂ��Ă͍���������̗v�͂Ȃ��Ǝv���B���̗��j�I���瓦���ɂ͋t�]���������肦�Ȃ��B���̋t�]���̓��_���l�����̗͂ł͍���ł���B�ǂ����Ă������̔_���l�̋��͎҂���˂Ȃ�Ȃ��B�t�����X�v���͂��̑��e�ł��������A����Ő����̃��_���l�͂��Ȃ������ꂽ�̂ł���B������ɁA�������̃��_���l�͈ˑR�Ƃ��Ē����ƕς��ʑ��݂ł������B���̂��߂P�X���I�ɓ����đ��e�̔����v���O�������l���邱�ƂɂȂ����B���ꂪ���\�_���̍\�z�ɂ����j�����Ȃ̎v�������֗����Ƃ����Y��ȃ��}���ł������B���ꂪ�}���N�X��`�ł���B �@�t�����X�v���̑��e�ł́A�L���ȁu���R�v�u�����v�u�����v�̃X���[�K���Ŕ_���l�̕s�����q�����܂����p�����̂ł������B�P�X���I�͂��������i�߂��킯�ł���B�����A���\�_�����\�z���Ă������^���A�Ȋw�Ƃ��ĐM�����܂��邱�Ƃ͕��ݑ��ł͂Ȃ��B������Ƀ��_���l�͏@�������ł���B�����ŏ@���I�����͂��ő���Ɋ��p�����B �������{�E���Y�����Ď�`�Ƃ͉��� �@���Ă��ꂪ�Q�O���I�ɓ���ƁA�푈�Ƃ�����i���P�X���I�I�Ȋv���Ƃ�����i�ȏ�ɗL���Ȃ��̂ƍl������悤�ɂȂ����B���ꂪ���[�j����`�ł���B�Ɠ����ɁA�_�o��A�S����Ƃ������ׂ��v���A�푈�̔@���g�D����K�v�Ƃ��Ȃ���i���l�������B �@�ߐ��j�͂��̉�X�̋t�]�v���O�����ɂ���đn��ꂽ���̂ł���B���ȏ��I�ȗ��j�ςł͉���������Ȃ����낤�B������v�ĉ�X�͗����Ď�`�ƌĂ�ł���B �@�v���ɂ��ϊv�����Y��`�����}���N�X�������Y�}�錾�A�푈�ɂ��ϊv�����{��`�������[�j�������鍑��`�_�A�}���N�X�E���[�j����`�Ƃ͂��̂悤�ȃ��_����������́u��i�v�u����v�ɂ����Ȃ��̂ł���B �@�������j�̔��W�@���Ƃ��Ĕ��荞�̂́A�ܘ_���_���l�ł���B���̂��ߋߐ��j�͍�������@���~��������Ɋׂ��Ă��܂����B�T�^�I�ȌP�b�w�҂̏�c�k��Y����s�j�N�O���ɂ͂ɂ킩�ɐM������Ƃł��낤�B �@�����̃v���O�����A�t�����X�v���ɂ�����ϊv�̎�i�́A�����I�ȃX���[�K�������ł������B�u���R�v�u�����v�u�����v�ł���B���̃X���[�K������{�����@�̍��q�Ƃ��Ď������̂���X���_���l�ł���B��҉���̂��߂̃X���[�K�������x�ȗ����I���Ɠ��{�֎������܂��Ɨ\�z���ɂ��Ȃ������������������������ƂɁA��X�͋C�����Ȃ������B �@����ł͑����̔����v���O�����ł���}���N�X��`�̐����ߒ��ɂ��Ď햾�������悤�B�}���N�X��`�̓}���N�X���\�z�����_���ł��邩��}���N�X��`�ƌĂ�Ă���A�Ƃ������߂���̂�����O�ƍl�����Ă���悤�ł���B�����������ɂ́A�}���N�X�ɂ����������������̋��\�_���̍\�z���˗����������傪����̂ł���B���̒����傪�}���N�X�ɑ������莆�A�������Ƃ������ׂ����̂�����O�ɐ��ɏo���̂ł���B����͓��{�ł��m���Ă���悤�ł���B�����A���ꂪ�}���N�X��`�̌����ł���Ƃ͑S����������Ă��Ȃ��悤�ł���B �@���ɏЉ��̂��A�����҂̃��_���l�o���j�b�V���E�����B�[�̃}���N�X�Ɉ��Ă��莆�̈ꕔ�ł���B �������\�����\�z�̈˗��� �@�u���V�A�͒c�����郆�_�����ꎩ�g�ł���B�F���̎x�z�͑��l��̓���ɁA�e�Ɨ���`�̏�ǂ��鍑���y�ьN�卑�̔p�~�ƁA���_���l�ɑ������Ɏs���I������F�ނ鐢�E���a���̌��݂ɂ���ĕۂ����ł��낤�B�S�R����푰�ł��S������̓`���I����������Ă���C�X���G���̎q���A���������ꍑ�Ƃ��`�����Ă��Ȃ��C�X���G���̎q���́A����n���̑S�\�ʂɊg���肱�̐V�����l�ގЉ�̑g�D�̗��ɓ���Ƃ��뉽��̒�R�Ȃ��w���v���ƂȂ�ł��낤�B��ɔނ�̒��̂���w�҂̌����Ȃ�w����J����O�ɉۂ���Ɏ������Ȃ�Ώ��X�̂��Ƃł���B �@���E���a�������݂����Ȃ�A���Ƃ̓������͖��Y�҂̏����ɂ���ĉ���̓w�͂�v�������ăC�X���G���l�̎�Ɉڂ�B�����ɂ����Ď��L���͓���Ƃ���������Y���Ǘ����郆�_���l�̎x�z�ɂ���Ĕp�~������Ɏ���ׂ��A�����ă��V�A�̎���̓������鎞�A���_���l�͑S���E�̐l���̍��Y�����̌��̉��ɏ������ׂ��Ƃ������_���`���̖͎�����������̂ƐM����B�v �@���̎莆�̈Ӗ�����Ƃ�����T������ƁA���Ȃ̃��V�A�v�z�̎����ɂ͐悸�A�_���l�A�܂�L���X�g���Љ�̌���ێ��̍Ԃł��鍑�Ƃ�]������K�v������B���������̍��Ɠ]���̍ő�̏�Q�͌N�吧�ł���B������������Đl�ގЉ�ɐV���������݂���B�܂胆�_�������ɂ��t�]���ł���B �@���ꂾ���ŏ\���Ƃ��l������͂������A����ɂ�����̍l�����������Ă���̂ł���B����̓��_�������ŗL�̗B���v�z�ł���B�����̒�����]��������͎҂���v�����^���A�[�g�ɂ��Ȃ�Ȃ��S���Y�����_���̂��Ƃɓ]���荞��ł���ł��낤�Ƃ����B�������A���̂��Ƃ̓��_�������̓`���I�ł���Ƃ������Ƃł���B �����u���V�A�v�z�v�Ɓu�^�����[�h�v���}���N�X��`�̌��� �@���āA�����ɂ̓��_���I�v�l�̍ł���ȂQ�̗v�f���܂܂�Ă���B �@�P�́A���V�A�v�z�̊�{�p�^�[���ł���B�I�����郆�_���������A�ً��k�Ƃ̊����ɏ��������߁A������N���������݂���Ƃ����I���_�ł���B���ꂪ�B���j�ς̌��^�ł���B�I���Ƃ̓v�����^���A�[�g�ł���A�ً��k���u���W���A�W�[�ł���B �@���ꂱ�����_���I�v�l�@�̓_�̌��^�ł���B����ɏ@���I�ϗ��ς����������̂ŁA�P���_�ƌĂ��킯�ł���B �@���V�A����S�������N�w�҃x���W���[�G�t�͂��łɁA�}���N�X��`�͏o���_�ɂ����Ėَ��^�I���i��L����ƕ��͂��Ă����̂ł������B �@�܂��A���{�ł͗�ؐ����������̒����w���j�I���Ƃ̗��O�x�ɂ����āA�u�B���j�ς͂��̍Ō�̋A���ɂ����ăv�����^���A�ƍق�z�肵�A���j�ُؖ̕@�I���W���~�g���邱�Ƃɂ���āA���̃G�X�J�g���M�[�I���_�Ɋׂ��Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���W�I�͊w�̘_���͂����ɂ����Ē�~���A�K���Η��̏��ŁA���Ƃ̉����ƂƂ��ɗ��j���܂��I�~����B����́A���_���I�I���ςƂ��̊O�`�ɂ����ċɂ߂č���������̂����邱�Ƃ��v�킹��B���Ȃ킿�A�v�����^���A�[�g�͐_�̑I���ɊY�����A�u���W���A�͈ٖM�l�ɊY������B���j�̓G�z�o�̑���ɁA�������l�Ԉӎu�Ɣ\�͂z�����A�o�ϓI�K�R�ɂ���Ďx�z�����̂ł���v�Əq�ׁA���Ȃ荎���ɖ{����˂��Ă���B���{�ł͋��炭�B��l�̉��ݘ_�҂ł��낤�B �s���_���E�L���X�g���ƃ}���N�X��`�j�ς̊�{�\���t 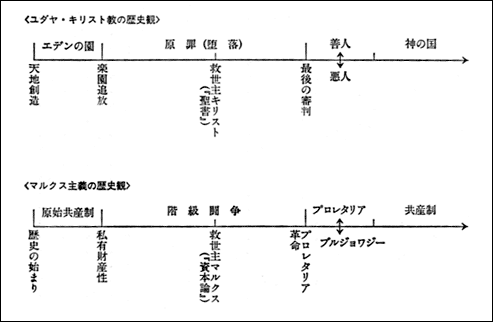 �@��̐}������A���_���E�L���X�g���i������w�u���C�Y���j�ƃ}���N�X��`�̗��j�ς��A���̊�{�\�z�ɂ����āA�����ɓ������̂ł��邩���A�������蒸���悤�B �@�}���N�X��`�ƃw�u���C�Y���������ɓ����y��ɗ����A������������ɂ��邩�͌����ȗL���҂������Ύw�E���Ă���Ƃ���ł���B �@���āA������̗v�f������̂́A���_���̖��@�Ƃ�������^�����[�h�̎v�z�ł���B �@����̓��_���l������́A���܂�Ă��玀�ʂ܂ŐM�O�Ƃ��Ă�����̂ł���B�^�����[�h�͂T�A�U���I���늮�����ꂽ���ɖc��Ȗ@�ł��邪�A�܂����{�ł͐�ア�낢��̃��_���l�A���{�l�ɂ���ďЉ��Ă���悤�ł��邪�A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̂����̍ł��̐S�ȂƂ��낪�Љ��Ă��Ȃ��悤�ł���B �@�̐S�ȂƂ���Ƃ����̂́A�u�V�����n���A���N�m�V���b�c�F���n�~�c�o�b�h��R�S�W���v�ł���B���Ȃ킿�u�_���l�̏��L������Y�͖{�����_���l�ɑ�������̂Ȃ�Ljꎞ�ނ�ɗa���Ă��邾���ł���B�̂ɉ���̉������Ȃ��������Y�����_���l�̎�Ɏ��ނ���Ȃ�v�Ƃ�����̂ł���B �@����̈Ӗ�����Ƃ���͑�ʂ��ĂQ����B�P�́A�u�ꎞ�a���Ă�����̂ł��邩��A�����Ȃł��㏞�킸�Ɏ��Ԃ��đR��ׂ����̂ł���v�Ƃ������Ƃł���A�����P�̓��_���l�̍��Y�͌̂Ȃ��_���l�ɒD��ꂽ���̂ł���v�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�O�҂������B�[�̃}���N�X�w�̎莆�̍��q�ƂȂ��Ă�����̂ł���B�܂�A���L���Y�̒D��Ƃ����v�z�͂������痈�Ă���̂ł���B����ɂ����P�̌�҂̉��߂̓}���N�X�̑��u���{�_�v�̍��{�v�z���Ȃ��Ă�����̂Ȃ̂ł���B�܂�A�u���_���l�̍��Y�͌̂Ȃ��_���l�ɒD��ꂽ���̂ł���v���炩�̗L���ȏ�]���l�������܂�Ă���킯�ł���A�u���v�ƃ}���N�X������������̂ł���B �����@���I�����͂����}���N�X��`�̖{�� �@�Z���I�ȃ}���N�X��`�̘_���I���́A�{���Ȃ���{�̃C���e���w�����ʂ��Ȃ��͂��͂Ȃ��Ǝv���B������ɉ��́A���̂悤�Ș_���I�����ɂ��S�炸�A���ꂾ���̐M�҂��W�߂���̂��Ƃ������ł���B �@����͏@���I�����͂Ƃ��������ł��Ȃ������̂��̂ł���B�}���N�X��`�̐^�̑f��͏@���Ƃ������Ƃł���B���{���Y�}�̑ԓx��������̂��Ƃ͂����킩��Ǝv���B�Ȋw�Ƃ����Ȃ���A���ۂ͌����Čo���Ȋw�̎�������悤�Ƃ��Ȃ��ԓx�������Ό����悤�B �@���Ă����ŁA���Y��`�҂̂����A�Ȋw�I�Љ��`�́u�Ȋw�v�Ƃ����`�e�����ǂ�����o�����Ƃ������Ƃł���B�ȏ���������@���}���N�X��`�����́u�Ȋw�v�Ƃ�����̂��A���̓������̍ۖ��炩�ɂ��Ă������B����́A�����B�[��̔M��Ȗ�����`�O���[�v����`�̂��ߐ����������̂ł���B�B���j�ς̂����u�Љ�̕K�R�I�Ȕ��W�@���v�Ƃ������Ƃ��������邽�߂ł���B�l�Ԃ̈ӎ�����Ɨ����������I�A�q�ϓI�����ɂ����j�͓��������B���������̖@���ɏ]���Ĉ��̕������������ē����ƁA�����ُؖ@�I�B���_���Љ�։��p�����B���j�ςł���Ɛ�`���Ă���킯�ł���B���\�̑傫���̂ɁA�������đ����̐l�X�͎��ȓ����Ɋׂ�̂ł��낤�B�A�J�f�~�b�N�Ȑ^���ȑԓx�Ə@���I�����͂̊�ȍ����Ƃ����悤�B �@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ���A���{�ōs�Ȃ��Ă���}���N�X��`�_���͕s�т̘_���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��A���{�̃C���e���w�͋��炭�}���N�X��`�̐����ߒ��������m�Ȃ������̂��낤����A�������Ȃ����Ƃ����m��Ȃ��B �@���S�ȋ��\�_���ł���A���Y��`�̖������Ղ��͈̂Ղ����B���\�������ɖ����ɂ��Ă͂߂悤�Ƃ���̂ł��邩��A���ׂĂ��̖����͘I������B�����A����ł��Ȃ����݂��}���N�X��`������������̂��Ƃ������Ƃ��𖾂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B �@�����Ƃ��A���̂悤�ȋ��\�_�����Ȋw�ƌ�F�����邾���̍����͂���ɂ͂���B����́u��ΓI�n�����v�Ƃ������݂ł���B�����I�A�o�ϓI�ɂ����舫���Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ���܂ōs�����A�Љ�͍��{�I�ɕϊv�����Ƃ��������͐����͂����낤�B���G�ȃ��J�j�Y�������l�ԎЉ�ł���B�ݔ���@�B�̔@���Â��Ȃ������炻������Ƃ肩����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B����������ł��A��ΓI�n�����̕K�R��������ΐl�ԎЉ�̕ϊv�ɑ��Ă������͂����Ƃ��B���̃}���N�X�̍l���́A���̂̌����ɐ}�ɓ��������̂ł���B �s���_���E�L���X�g���ƃ}���N�X��`�̑������t 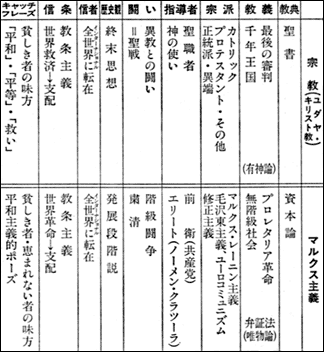 �@��̕\�����Ē�����A�}���N�X��`�������ɏ@���I�Ȃ��̂����������蒸���悤�B�L�_�_���B���_���̈Ⴂ�������A���炩�Ɉ�_���I�v�z�i���_���I���E�ρj�̃R�s�[�ɉ߂��Ȃ����Ƃ�������B �@���������̗B���_�́A�L�_�_�̂��g�����h�Ɓg���E�h�ɑ��锽���Ƃ��ďo�Ă�����̃C�f�I���M�[�ł���A�L���X�g�������͂�����������́u��֏@���v�i�[���@���j�ɉ߂��Ȃ��B�܂�ꌾ�ŏq�ׂ�Ȃ�A�}���N�X��`�Ƃ́A�P�X���I�̃��[���b�p������w�i�ɂ����A����n��ɂ�����A�ꎞ�I�ɔ��������@���ł���Ƃ�����B �@�C�M���X�̗L���Ȑ��E�I���j�w�҂ł���A�[�m���h�E�g�C���r�[���m�́A�u�}���N�X��`�̓L���X�g���̈������v�ƌ��������A�����́u�_�v�̗͂��r�����Ă�������ɁA���[���b�p�l�͎��Ȃ�u�����v�Ƃ��āA�}���N�X�E���Y��`������A�}���N�X�́u���z�������Y���Љ�̎����v�Ƃ����g�\���h��M�����̂ł���B �����B���j�ςɏ]�����Y�}�́u�������v�^�������ׂ��� �@���Y��`�҂́A�����Ƃ����Ƃ����u�}���N�X�͂��������Ă���v�ƃ}���N�X��[�j���̌��T���瓚���o���Ƃ����Ă���B�P�b�w�I�A�v���[�`�̍D���Ȕނ炪���̐[�݂ɂ͂܂邱�ƂɂȂ�͓̂��R�ł��낤�B�����̓��ōl���Ă��Ȃ��B�����̓��ōl���Ă���ΌP�b�w�I�ԓx�Ɋׂ邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�������ނ炪�����������Ӑ[���A�v���[�`���Ƃ��Ă���A�u���Y�}�錾�v�u�o�ϊw�ᔻ�v�u���{�_�v�Ƃ����}���N�X�̌��T�̔��\�����ɋC���Ƃ߂�ł��낤�B���_����ɏo���ꂻ�̐�������ɑ����Ƃ������Ƃ͉����ł͂Ȃ��̂��B�܂�����́u�����v�ɂ����ẮA�����B���j�ςɐ^�ɒ����Ȃ�A��ΓI�n�����������Ă����v���̃`�����X�͐��܂��̂ł��邩��A�u�������v�^�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���B���������{���Y�}�͂��āu�������v���f�������Ƃ͈�x���Ȃ��悤�ł���B����ȊȒP�Ȗ����ɂǂ����ċC�����Ȃ��̂��B��������Ƃ���A�P�ʁE���ʘ_�̂����炵�߂�Ƃ���Ƃ��������悤���Ȃ��B �����B���_�A�ϔO�_�ɂ������ґ�������� �@�������ł����{�I�Ȗ��́A�_�ɂ��B���_�ƊϔO�_�̓�ґ������������邱�Ƃł���B �@�}���N�X��`�̋��ȏ��͂��̓_������傳����悤�ɂ��Ă���̂���Ƃ���B �@���ʂƂ��ėB���_��ۉ��Ȃ��ɑI���������A��������ׂĂ̓y��Ƃ��čl����������B��������ɕ�������������B�܂�A�@���Ȃ鎞�ł����ԂƂ������̂̑��݂�F�߂Ȃ��B �@�����A�N�w�I�ɂ͗B���_�ƊϔO�_�͓�ґ���]�X�̖��ł͂Ȃ��B���_�ɂ����Ă��łɓ_�I�v�l�Ɋׂ��Ă���킯�ł���B���R�̋A���Ƃ��ėB���_��ΗD��Ƃ������Ƃɓ������B �@���̌��ʁA�Љ�I���݂��ӎ������肷��Ƃ����e�[�[������B���������āA�푈���v���������I�A�o�ϓI�v���ɂ���Ă݈̂����N���������̂ł���Ƃ�����Θ_�ɓ������B �@���ꂪ�}���N�X��`�̍ł��̗v�ȓ_�ł��邱�Ƃł���B���_���炵�Ă��̒��q������A�Ȍ�o���Ȋw�̎��ȂǍl���������Ȃ��Ȃ�̂ł��낤�B�܂��A���������ӖړI�ȓ�ґ���������ł���̂͏@���I�����͈ȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��Ƃ������Ƃ��^���ł��낤�B �����u�鍑��`�_�v�̓��_��������`�҃��[�j���̐��헝�_ �@���ɁA���[�j����`�ɂ��ďq�ׂ悤�B �@���{�̊F�l���܂����������ƂɂȂ邩���m��Ȃ����A���[�j���̓��_���l�ł���M��ȃ��_��������`�҂ł������B���̓_�̓}���N�X�ɗ��Ȃ����낤�B�����I�ɂ͕��n���Ñ��̃J�����C�b�N�l�ł���A��n�����_���l�ł���B�N���[�v�X�J���v�l�͏����̃��_���l�ł������B �@���ȏ��I�}���N�X��`�ł́A���[�j����`�Ƃ̓}���N�X��`�����{��`�̍ō��i�K�A�鍑��`�̎���ɓK�p�A���W���������̂Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���O�_���炢�������Ƃ������邾�낤�B�������{���_�͂���Ȃ��Ƃł͓��ꗝ���ł��Ȃ����낤�B �@���[�j���Ƃ����ƁA�v���ƂƒN�����l���邾�낤�B���������ۂ́A����ƂƂ����ׂ��ł��낤�B���[�j���Ƃ����u�鍑��`�_�v�ł���B���́u�鍑��`�_�v�Ƃ����̂́A�{�l���F�߂Ă���@���A�z�u�\���́u�鍑��`�v�̓���Ƃł������ׂ����̂ł���Ǝv���Ă���B���������͂���ȂƂ���ɂ���̂ł͂Ȃ��B�S���̒��̂�����s�A�u�鍑��`�����Ԃ̐푈�͕s���ł����v�Ƃ����_�ɒ��ڂ���������悢�B���[�j�����u�鍑��`�_�v���������ړI�͂������̈�_�ɂ���̂ł���B �@���̖ړI�́A�푈�Ƃ������̂����_�������̉�����Ƃɍł��L���Ȏ�i�ł���Ƃ������Ƃɂ���B�P�X���I�̃}���N�X�̎����o���������R���ɂ�鍑�Ƃ̓]���Ƃ�����i�����A�����Ǝ����葁����i���푈�Ȃ̂ł���B�푈�ō��Ƃ��敾�����ǂ���������Ԃ̕ϊv�A������Ƃ̃`�����X�ł���Ƃ������Ƃł���B���{�̐����v�����̃p�^�[���ł���B �� �@���Ă����ŁA���[�j�����M��ȃ��_��������`�҂ł���Ƃ������Ƃ̏؍��Ƃ��Ď����������������B���ʃ}���N�X��`�ҏ��N�͒��ڂ��Ă��Ȃ����̂��肾���A���_������_���鎞�̃��[�j���̌����͑z���ȏ�Ɍ��������̂�����B �@�P�X�P�R�N�W���P�W���t�́w�Z�[�x���i���E�v���E�_�x����Ń��[�j���́A���V�A�ł̓��_���l�w�Z�̖����ʉ��𐄐i���悤�Ƃ��Ă���Ƃ��āA����ɔ��������Ă���B��ӂ��̔@���ł���B �@�u���V�A�ɂ����郍�V�A�����͑S�̂̂S�R�����߂�ɂ����Ȃ��̂ɁA�����烍�V�A�����ɂ����������^���悤�Ɠw�͂��Ă���B�����ă��V�A�ݏZ�̑������A������^�^�[���l�ɑ��Ă܂��܂��ނ�̌���������߁A��������𐄂��i�߁A���݂ɔ��ڂ�����悤�Ȑ�����Ƃ����B���̍ł��ɒ[�Ȍ���ꂪ�A���_���l�w�Z�̖����ʉ�����ł���B���̓��e�́A�����A�������Ƃ킸�A���ׂĂ̊w�Z�Ń��_���l�ɖ�˂����S�ɕ������Ƃ��Ă���A���̂��߃��_���l���w���̐���S�����Ő������悤�Ƃ��Ă���B���[���b�p�ł͒����ɂ������݂������̂悤�ȍ��ʐ������������n�߂悤�Ƃ��Ă���B�v �@���ʁA�_���l���A���_���l�̍��ʂ����̂悤�ɔM�S�ɔ��A�ᔻ���邱�Ƃ͗Ⴊ�Ȃ��B���_���l�łȂ���ł�����̂ł͂Ȃ��B �@�w�C�X�N���x�̂P�X�O�R�N�Q���P�T�����̒��ŁA���_���l�J���ґ������A�ʏ́u�u���h�v�����咣�ŁA�u���_���l�v�����^���A�[�g�ɓƎ��̐��}���K�v���v�Ƒ肵�Ę_�����Ă�����̂����邪�B �@���̘_���̒��Ń��[�j���́A�V�I�j�Y����җ�ɍU�����Ă���̂ł���B�V�I�j�Y���Ƃ̓n���K���[���܂�̃W���[�i���X�g�A�e�I�h���E�w���c�����m���h���t���X����������ɂ����_���l�͌��ǎ����̃i�V���i���z�[�������݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ��S���A�c��̒n�A�V�I���̋u�A�p���X�`�i�A�낤�Ƃ���^���ł���B�܂茻�݂̃C�X���G�������̃V�I�j�Y���^���̌����ł���̂͂����܂ł��Ȃ��B �@�ł̓��_���l���[�j���͉��́A���̗��z�I�ȃV�I�j�Y���^�����U������̂��B���_���l�̉^���ɂ͂����P�������̂ł���B����̓}���N�X�̏�����v���A���[�j�����g�̏�����푈�A���̂Q�{��g�ݍ��킹�ė����Ď�`�Ƃ����̂����A���̐�����̃��_���l�̗��z�̎����Ƃ��������������̂ł���B�����ɂ����A�O�҂��n�g�h�A��҂��^�J�h�Ƃ����ׂ����B���[�j�����g�͖ܘ_�A���[�j����`�Ƃ����@����҂̃^�J�h�H���̗v�ł���B�w���c�����m�̏�����i�V���i���z�[�����݉^���̔@���͔������ɂ����Ȃ����낤�B �@���O�_�̃}���N�X�E���[�j����`��_����̂ł���A�Ȃɂ��V�I�j�Y���^���̔@�����_���l�����̉^���ɘ_�y����K�v�͖ѓ��Ȃ��͂��ł���B�v�킸�{�����o���Ƃ����Ƃ���ł��낤���A��������_���l�łȂ���ΐ�ɏo�Ă��Ȃ��_�ł��낤�B �@���̃u���h�U���̘_����ʂ��Č����邱�Ƃ́A���炩�ɓ��ւ̃P���J�Ƃ������������v���v�����Ă��邱�Ƃł���B���ꂪ���O�_�Ƃ��Ẵ}���N�X��`��_���郌�[�j���Ɠ���l�����Ǝv�킹��قǂ̓����ӎ��܂邾���̌������т��Ă���Ƃ������Ƃł���B �@ �������{�l�̒m��Ȃ��u���V�A�v���v�̎��� ���ɁA���V�A�v�����v�����^���A�v���ƌ��O�_�ɏI�n������̂́A�����ł͓��{���Y�}�ȊO�قƂ�ǂȂ��Ȃ������A���V�A�v���̖{���ɂ��ĊȒP�ɐG��Ă������Ƃɂ���B �@���{�ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����A�������Ă̐V���_���̓��V�A�v���Ƃ͂��킸�A�u���V�A�E�N�[�f�^�[�v�ƌĂ�ł���̂ł���B�܂�A�N�[�f�^�[�͊v���Ƃ������Ď���������ꂽ�����̂��̂ł���B���_�����͂��c�@�[���͂ɂƂ��đ��������̂Ƃ����Ӗ��ł���B����̓t�����X�v���Ɏ������_���l�̔����v���O�����̑��e�������̂��B �@���̃��V�A�v���͗\������Ă����Ƃ����悤�B�P�X�P�R�N�P�O���A�E�B�[���Ŕ��s����Ă������_���@�֎��w�n���}�[�x��Q�V�S���Ɏ��̂悤�ȋL��������B �@�u�c�@�[�̓L�G�t�ɂ����ă��_���l�ɑ���O��I�Ȗo�Ő�������c�����B�^���͂��̑哬���̌��ʂɂ������Ă���B����������̓��_���l�̉^���ł͂Ȃ��B���̂Ȃ烆�_���l�͕����邱�Ƃ��Ȃ�����ł���B����͂����c�@�[�̉^���ɂ����Ȃ��Ƃ��������̂��Ƃł���B�c�@�[�̏����͂��̏I���̔��[�ɂ����Ȃ��B����铹�͂Ȃ����Ƃ�m��ׂ��ł���B���̂��Ƃ��悭�̂ݍ���ł����B��X�̓L�G�t�ɂ����āA�S���E�Ɍ������Ă���ɕ��J������������̂�e�͂��Ȃ����Ƃ��������B�������_���l�����܂łɃ��V�A�Ɋv�����N���������B��������Ƃ��Ă����̂Ȃ�L�G�t�����ɂ�����c�@�[�̑ԓx�������������A���̐���͎̂Ă�ׂ��ł���B���̎����̌��ʂ��ǂ��ł��낤�ƁA�c�@�[�ɑ��Ă͗e�͂��Ȃ��B���ꂪ��X���_���l�̌��S�ł���B�v �@����͎��M�ɂ��ӂꂽ�\���ł���B���̂悤�ȏɑ��Ă͌x���_���ܘ_�o�Ă���B���̈��Ƃ��āA���I�I�����_���g�E�[�f���f�B�N�͉p���O���o���t�H�A�ɑ��Ď��̔@���𑗂��Ă���B �@�u�{���V�F���B�L�ɑ��ẮA���݂₩�ɒe���������˂Ȃ�Ȃ��B���̂܂܂��ƑS���E�ɂ��̓ʼn�͍L���邾�낤�B�{���V�F���B�L�͍��Ƃ������Ȃ����_���l�Ɍې�����Ă���B���̖ړI�̓��_���l�̗��v�̂��߂Ɍ���̕ϊv��_���Ă���̂ł���B���̊댯���~���̂͗̋����s���݂̂ł���B�v �@����ɑ��Đe���_����`�ҁA�p�����C�h�E�W���[�W�ƃA�����J�哝�̃E�b�h���[�E�E�B���\�������łɔ��������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B �� �@�P�X�Q�O�N�j���[���[�N�̃��V�A�l�̖S���c�̂ł���u���j�e�B�E�I�u�E���V�A�v�̓\�A�̎x�z�ҒB�̐l���^���o�ł��Ă��邪�A����ɂ��Ɠ����̃\�A���{�̊e�ψ���ɐ�߂郆�_���l�̐��y�уp�[�Z���e�[�W�͎��̔@���ł���B 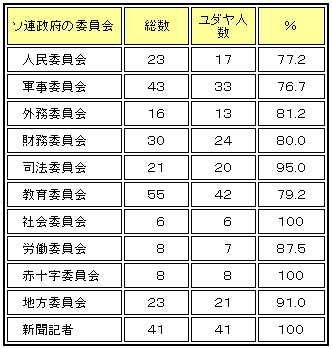 �@���ɉp���w���[�j���O�E�|�X�g�x�̔��\�����\�A�̍����ψ��̒��̃��_���l�ɂ��Ă̖{���ƋU���i���V�A���j�̃��X�g�������B �����[�j���@�i�E�����[�m�t�j ���g���c�L�[�@�i�u�����V���^�C���j �����V���R�t�X�L�[�@�i�S�[���h�o�[�O�j ���J�[���l�t�@�i���[�[���t�F���g�j ���W�m�r�G�t�@�i�A�v�w���o�E���j �����W�F�k�L�C�@�i�N���b�V���}���j ���X�e�N���t�@�i�i�n���P�X�j �����f�b�N�@�i�]�[�x���\���j ���_�[�Z�t�@�i�h���v�L���j ���X�n�m�t�@�i�M�������j ���S�[���t�@�i�S�[���h�}���j ���}���g�t�@�i�[�f���o�E���j ���{�O�_�m�t�@�i�V���o�[�X�^�C���j �����g���B�m�t�@�i�t�B���P���X�^�C���j �@�����̏؋����݂Ă��킩��ʂ�A���V�A���ςƂ������̂����_���l�̉���^���������̂��B �@�����I�ɓ����Ă̊v���^���Ƃ������̂́A���_���l�̋ꂵ�߂��Ă������X�ŋN���Ă���̂ł���B���V�A�R��A�h�C�c�R��ł���B�t�����X�v���̌��ʁA������x�̎��R�����_���l���l�������t�����X���̑������A���_���l�Ɋ��傾�����X�J���W�i�r�A�����A���_���l���o�ϓI�h���v���ȂǂɍI�݂ɗ��p����p��S���Ă����A���O���T�N�\�������Ȃǂɂ����Ă͊v���^�����قƂ�NjN�����Ă��Ȃ��̂ł���B�������ꂪ�Љ�̔��W�@���]�X�Ƃ������ƂȂ�A�ϓ��ɋN�����đR��ׂ��͂��ł͂Ȃ����B �����A�����J�̓\�A�̏��Y�w�Ƃ�����͉̂��̂� �@���V�A���ς̐����̓A�����J�̉����ɕ����Ƃ��낪�^�ɑ傫���̂ł���B �@�����̕ă\�W��������Ȃ��l�͋�����邾�낤�B�����Ƃ��̂��Ƃ�������Ȃ��B���݂̃A�����J�ƃE�B���\�����ォ�烋�[�Y�x���g����܂ł̃A�����J�͍��{�I�ɈႤ�Ƃ����邩���m��Ȃ��B�ꌾ�ł����A�����̃A�����J�̓��_�����͂����ɋ��������̂ł���B�W���[�E�G�X�E�G�C�Ƃ���ꂽ���̂ł���B���{�ł͗�P���Ƃ����Ă������������B���_���l�ł͂Ȃ����e���_����`�҂̃E�B���\�����A���V�A���ςɂ͔��ȓw�͂�ɂ��܂Ȃ������̂ł������B �@���E�̋����N�[���E���[�u����̃��R�u�E�V�t�́A�g���c�L�[���ʂ��ē����̋��łP�Q�O�O���h���Ƃ���������o���Ă���B�V�t�����I�푈�̎����{�ɑ݂����̂��ړI�͓����ł���B �@���_���l���Z�Ǝ҃��R�u�E�V�t�́A�A�����J�E���_���l�̒��S�I���݂������B �@�܂��A�����J���{�͌X�̊v���Ƃɂ��X��^�����̂ł���B�c�@�[�̒e���̌��������������A���V�A�ł̃��_���l�v���Ƃ͂��낢��ƍs���𐧌�����Ă����͓̂��R�ł���B�����ŃA�����J���{�͂���烍�V�A�̃��_���l�v���Ƃ���U�A�����J�ɓ��������A�A�����J�̎s������^���čĂу��V�A�֑���Ԃ��Ƃ�����̍����Ƃ����ł������̂ł������B�����A�����J�s���������������_���l�v���Ƃ́A�������ۊW�ɂ����Ďォ�����c�A�[�̃��V�A�ł͎��O�@�������������̂̔@���ӂ�܂����̂ł������B �@����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ͂܂����ɂ�����B �����ČR�̃V�x���A�o���̐^�̈Ӗ� �@���{���V�x���A�o�������c���������A�E�B���\���͕ČR�̔h���\���Ă���B����̓{���V�F���B�L�A�܂胆�_�����̗͂i�삪�^�̑_���������̂��B �@����Ƃ����P�́A���{�̋ɓ��n��ł̐L����W�Q���邱�Ƃł������B����̓��_���������i�V���i���z�[�������n�Ƃ��Ė��B��_���Ă������Ƃɑ��鑤�ʉ����ɑ��Ȃ�Ȃ��B �@�r���r�W�����Ƀ��_���l���A�n���������̂��A�}�N���ɍl����Ζ��B�ւ̃��_���l�i�o�ɑ��鋴���Ƃł���A�~�N���ɍl����A�����J�Ƃ̐ړ_�����邱�Ƃł������B 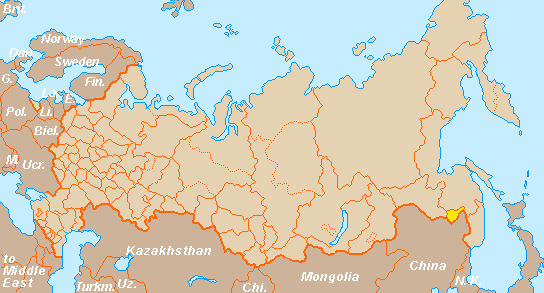 �ɓ��n���ɑ��݂���r���r�W�����̃��_���l���A�n�i���F�ɓh��ꂽ�n�恪�j �@���̕ČR�ɂ͊�ȕĕ��������ȏア���B�p���b���Ȃ��ĕ��ł���B���̂��B�ނ�̓|�[�����h�o�g�̃��_���l�������̂ł���B�ނ���܂���������A�����J�֓������A�A�����J�s���������炢�A�ČR�̕��𒅂ăV�x���A�֒y���Q�����̂ł���B���̈Ӗ��ł��A�A�����J�͂܂��Ƀ\�A�̏��Y�w�Ƃ����悤�B �@���V�A�v�������̂悤�ȊO�I���͂ɂ���Đ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ͂������肢���������Ǝv�����A���I�ɂ́A��قǂ̃����B�[�̃}���N�X�ւ̋��\���݂̔������ɂ���ʂ���s���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ́A���ʂ̃}���N�X��`�̌��O�_�Ɋ�Â������ȏ��ł�������ʂ�ł���B �q�����r �����B���j�ς̓��_���_�b���� �@�}���N�X�̖��͊w�҂ɂȂ邱�Ƃł������B���̂悤�ȃ}���N�X�̂��Ƃł���A�P�Ȃ�\���҂ł͌����Ė����ł��Ȃ��������낤�B�����ɂ���Đ悸�w���Y�}�錾�x�̋��\�n�C�|�Z�V�X���\�z�������A���̒P���ȉ��݂ł������ł��Ȃ��B�����Łw�o�ϊw�ᔻ�x�������̂ł��邪�A���̑��̖ړI�͌���̕ϊv�����L�@�I�ɐM�����܂��邱�Ƃł���B �@����A�܂莑�{��`������̂����Y��`�ɕϊv����Ǝg�t�i�������j���邾���ł͏[���Ȑ����͂�����̂Ƃ͂����Ȃ��ƍl�����킯�ł���B���̂��߂ɂ͎��{��`���Œ肵�����́A�Î~�������̂ƍl�����Ă͂܂����B����𗬓��I�Ȃ��́A�K�R�I�ɕς�闬��̒��̈ꎞ���ł���Ɛ������Ƃ��L���ł���B���̂��߂ɍl�����̂��u�Љ�W�i�K���v�Ȃ���̂ł���B���n���Y�Љ�Ñ�z�ꐧ�Љ�����Љ���{��`�Љ���Y��`�Љ�Ƃ������̂ł���B�w���{�_�x�ŗp���Ă��錾�t�ł����g�ϑԁh�Ƃ������ƂɂȂ�B �@����̓��_���_�b�̃p�^�[���ł���B�ŏ��ɒ��a��ۂ����_��̎��オ����A���ꂪ�ً��k�ɂ������ꂽ���Ō�ɂ܂����a�̕ۂ��ꂽ���Ȃ����̎���Ɏ���Ƃ������̂ł���B������}���N�X�́A���n���Y���Љ�ƍŌ�̋��Y��`�Љ�̊ԂɂR�̊K�������̂���Љ������Łu�Љ�Ȋw�v�Ƃ��Ĕ���o�������̂ł���B���ꂾ�Ǝ��{��`�Љ�͊K�������̉Q���ɂ����i�K�Ƃ��ĉf��A�����I�ɉf��B���������āA�ϊv�͕K�R�Ɛ������₷���B �����ł�����ƃC���^�[�ɂ��ĐG��Ă������B �@���̃C���^�[�i�V���i���Ƃ����̂̓��_���l�̉��̘A�т̂��Ƃł���A���{��ł����u���ہv�Ƃ����ϔO�Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�B���_���l�͍��Ƃ������Ȃ������̂ł��邩��A�C���^�[�i�V���i������݂̂ł���B���Ƃ������������������u���ہv�Ƃ͎������������̂ł���B�������A�}���N�X��`�̌��O�_��ӐM����l�X�́A�u�v�����^���A���ێ�`�v�Ƃ������\��M���ă��_���l�Ɠ��l�ɍ��Ƃ�ے肵�ĊK���Ԃ̉��̋��h���̕������Ƃ��D�悷��ƍl���Ă���B���ꂪ���ςł��邱�Ƃ͒��\�Η��A���z�푈������Ζ����Ȃ��Ƃł���B �����v�����^���A�Ƃ́g�q���������Y�̂Ȃ��ҁh�̈� �@���ۃ��_�����͍͂����I�ɓ����Ă�����A���ӂ̗����Ď�`�̈���̗Y�Ƃ��āu�v�����^���A�[�g�v�Ȃ�K����n�����A���Ƃ������������邽�ߊK�������Ȃ���̂��g�t���Ă����B����̓��e�����Proles���q���Ƃ����Ӗ��̌��t����o�Ă�����̂ł���A���̈Ӗ�����Ƃ���́A�q���������Y�̂Ȃ��ҁA�܂�Â����t�ł����Ƃ���́u���Y�ҁv�ł���B�܂��ʂ̈Ӗ��ł́A�q���Y����ȊO�ɔ\�̂Ȃ����́A�܂�u���Y�ҁv�͉������Y���Ȃ����̂Ƃ����Ӗ��ɂ����_���l�͍l���Ă���̂ł���B�܂�A���̗p��ɂ̓��_���l�̕��̓I�Ӗ������߂��Ă���̂ł���B �@ �������{�_�̌������^�����[�h �@�u���Y�}�錾�v�u�o�ϊw�ᔻ�v�Ɨ\���I���\���݂������Ă����}���N�X�ł͂��������A�{���w�Ҏu�]�̃}���N�X������ɖ�������͂����Ȃ��������Ƃ͂ނ��듖�R�Ƃ����ׂ��ł��낤�B �@��p�����ق֒ʂ��������n�߂��}���N�X�ɂ��āA�ɕn��Ԃ̒��Łw���{�_�x�̎��M�𑱂����Ƃ����_�b���]����ʓI�ł������B�ŋ߂ł́A�}���N�X�������Ɏq�����h���A�G���Q���X�������F�m���Ă����Ƃ�������������݂ɏo�Ă����B����Ȃǁu�_�b�v��M������ł����l�ɂ͐M�����Ȃ����Ƃ��낤�B���́A�ɕn��Ԃ̒��Ő������Ă�����̂������Ȃnjق���̂��A�Ƃ����^�₪�悸�o��ł��낤�B �@�����A�}���N�X�̎����̓��_���̑g�D���狐�z�̎����Ă����̂ł���B�}���N�X�������h������ɏZ�\�[�z�[�ɂ���Z���͌��㗬�ɂ����Γs�S�̍����}���V�����Ƃ������ׂ����̂ł���B�\�[�z�[�n��͂P�X���I����͌��݂̂���Ƃ������č����Z��n�ł������B�}���N�X�́A���̂悤�Ȍb�܂ꂽ���̒��ł䂤�䂤�Ɩ����̎���ړI�̂��ߋ��\���݂̑n��ɂ������Ă����̂ł������B �@�����Ń}���N�X���n�삵���w���{�_�x�͓��{�ł́u�o�ϊw�̌n�v�̒��֑g�ݍ��܂�Ă���悤�ł���B�}���N�X��`�Ƃ������������́w���{�_�x���Ȃ�������A��������З͂����邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��B�u���Y�}�錾�v��u�o�ϊw�ᔻ�v�ł́A�w��̌n�Ƃ��Ă܂��߂ɍl����킯�ɂ͂����Ȃ��ł��낤�B �@������ɂ��́w���{�_�x���ꌩ�w�╗�̑�����g�ɂ��Ă��邽�߁A�}���N�X��`�Ƃ������̂�����قǑ傫�ȉe���𐢊E�j�ɗ^���邱�ƂɂȂ����Ƃ����悤�B �@�������A���́w���{�_�x�͌X�̕����Ɋw���I�ԓx�̔��f�����o����邱�Ƃ�ے�͂��Ȃ����A�߂������ȁA�S�̂𗬂��v�z�̓}���N�X��`�S�̂̏ꍇ�Ɠ������A���V�A�v�z�ƃ^�����[�h�̎v�z�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���_���A�e�_�^���Ƃł����������B��͂肱����A�\���҂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł���B �@���{�ł́w���{�_�x�̌������x���͑����Ɣ�ׂăP�^�O��ɍ����Ƃ�����B�w���{�_�x�����Ƃ������ƂɂȂ�A���́u�\���ҁv�̔��z�̌����A�\�z��Ƃ̉ߒ��A�ړI�Ȃǂ̉𖾂ɏœ_�ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂����A���̂��u�o�ϊw�v�ɑ���P�b�w�I�ԓx�������{�ł͌����Ȃ��B �@�}���N�X����A�̗\���҂̂����߂Ƃ��āA�܂������Ƃ����Ȃ̊w�҂Ƃ��Ă̗~���������߂ɗ]����ł����̂����́w���{�_�x�ł��邪�A�}���N�X��`�Ɠ������u�n�߂Ɍ��_���肫�v�Ƃ����ނ��ł���B���_���A�v���I���ɏo����Ă��܂��Ă���B�A�v���I���ɏo���ꂽ���_�Ƃ́u�v���v�ł���B���������āA������A�[�I��@�ł͖��{���肷�邵���Ȃ��̂ł����āA��㈓I�ɕ�������K�v������B �q�����r �@ �����u���v�̈Ӗ��ƌꌹ �@�}���N�X��`�\�z�̌��_�ƂȂ����̂��^�����[�h�̎v�z�ɂ���Ƃ��������A�w���{�_�x�ɂ����Ă������ł���B �@�ĎO�J��Ԃ����p���ċ��k�ł��邪�A�u�_���l�̍��Y�͈ꎞ�ނ�ɗa���Ă�����̂ł���v�������_�͍��������悤�Ɂu�v���v�ł��邪�A���_�͂�͂肱������n�܂�B �@�w���{�_�x�̒��ł��L���Ȃ��̏�]���l�̖@���Ƃ����̂�����ł���B�}���N�X�͂�����u���v�ƌĂ�ł���ƈ�ʂɂ͂����Ă���悤�����A�}���N�X�̓��ɂ͂��́u���v�̕�����ɂ������̂ł���B�O�q�̃^�����[�h�̎v�z���悭�l���Ă݂�Ɓu�{�������B�ɑ����锤�̍��Y�����s�s�ɂ����݂͑��l�̎�ɂ����v�B���̍l�����u���v�Ƃ������t�̌����ł���B �@Ausbeutung �Ƃ����h�C�c�ꂪ����B���ʂ���͓��{�Łu���v�Ƃ����Ă��錾�t�ł���B���� usbeutung �Ƃ������t�́A�����ɂ����ă��_���l�ɓ�������ꂽ���t�ł������B�����ɂ����Ă̓��_���l�ɋ����ꂽ�B��̐��Ƃ͍����݂��ł������B�����݂��Ƃ�������ȐE�Ƃ��炵�āA���̏��@�͂��������Ȃ��̂ɂȂ炴��Ȃ������B���̓���ȃ��_���l�̏��@��_���l�� Ausbeutung �Ƃ������̂ł���B �@����Ȗ�����`�҂ł���}���N�X�����̕s���_�Ȍ��t�������͔_���l�ɓ����Ԃ��Ă�肽���Ɣ邩�Ɏv���Ă����Ƃ��Ă��A�Ȃ��s�v�c�͂Ȃ��ł��낤�B �@�}���N�X�̍l���ł́A�{�������B�ɑ�������̂��̂Ȃ��D���Ă���̂ł��邩�炻������Ԃ��͓̂���O�ł���B������ɍ����݂��̔@�����X������D�ł����������u���v�Ƃ������t�𓊂����Ă���B����͊��ɍ���Ȃ��A�ƍl����͎̂��R�ł��낤�B �� �@�ȏ�̂��Ƃ��A�}���N�X�Ɂw���{�_�x���������悤�ƌ��ӂ������ő�̓��@�ł���ƍl������B�悸�ŏ��ɁA�̂Ȃ��D���Ă�����̍��Y����̓I�ɐ������悤�Ƃ���Ƃ��납��w���{�_�x�͎n�܂�킯�ł���B�܂�A�^�����[�h�̎v�z���u�_���I�Ȉ߁v�𒅂��邱�Ƃ���n�܂�킯�ł���B �@���ꂪ��]���l�̖@���ł��邪�A����͘_���I�ɍl���Ă��l�ԎЉ�ɂ��Ă͂߂�ׂ����̂ł͂Ȃ��A�a�Љ���I�Љ�ɂłł����Ă͂߂�ׂ����̂ł���B�������������l�ԎЉ�ł͂��̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����͗B���j�ςɂ��Ă������ł���B�������}���N�X�ɂƂ��ẮA���Ƃ��Ƙ_�����Ȃǂǂ��ł��������Ƃł������B �@���̏�]���l�_�̍\�z�ɂ́A�}���N�X��`�̍\�z�̎��Ɠ������Q�̃��_���v�z�����̂���Ă��̌����ƂȂ��Ă���B�܂���ɕ����_�𗧂Ă邱�Ƃł���B���̂��߁A���V�A�v�z�َ̖��^�A�u�I���v�u�ً��k�v�̊����ɂ��G�X�J�g���M�[�i�I���_�j�Ƃ����}���ł���B �@�v����Ɂu�J���ҁv����̓��V�A�v�z�́u�I���v�A�܂胆�_�������ɑ�����������̂ɂ����Ȃ��̂����A�J���ҁA�������_�����������s�s�ɍ��Y��D���Ă���Ƃ������ƁA���������Ď�i��I��������Ƃ�Ԃ��͓̂��R�ł���Ƃ����u�_�����v�̈߂ł����ĐM�����܂���ΖړI�͒B����킯�ł���B �@���ĈȑO�ł͂��̂��Ƃ��ؖ�����@���Ȃ�ޗ������o���Ȃ������̂ŁA�}���N�X�������������ăn�C�Q�[�g�p�[�N�ɖ��邱�Ƃ��ł��������m��Ȃ����A�����ł͂����������Ȃ��Ȃ����悤�ł���B �@���{�_�͗B���j�ς̓��t���̖���^����ꂽ���̂ł���B���������āA�B���j�ςƓ�������ΓI�n�������@���ɂ��ĕK�R���������̂��Ƃ������Ƃ��������̂�ړI�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͓��R�ł���B �� �@�}���N�X�̓^�����[�h�̑O�q�̎v�z�ƃ��V�A�v�z�َ̖��^�̃p�^�[�������ɂ��܂����т������̂��Ɗ��S����B�����A���z�̌��_�͔��ɑ씲�Ȃ��̂ł��邪�A���_�A�܂��ΓI�n�����Ɗv���Ɏ���r���̉ߒ��ɂ͖��Ă͂Ȃ��������̂ƌ�����B���Y�͂Ɛ��Y�W�̖����Ƃ����̂��}���N�X�����̃v���Z�X�ŗp�������݂ł���B �@���Y�W�Ƃ����̂̓��V�A�v�z�̓�l�_���ɂ���ɕ����Ńu���W���A�W�[�ƃv�����^���A�[�g�̊����Ƃ������Ƃł��܂��ݒ�ł������i���Ȃ��Ƃ��}���N�X�Ȃǂ͂����v���Ă��邱�Ƃ��낤�j�A���Y�͂Ƃ����͔̂��ɋꂵ���͂Ȃ����B���̐��Y�͂Ƃ����͖̂c���������Y�͂Ƃ����ӂ��ɐݒ肳��Ă���B�܂�A�L���Ȑ��Y�͂ł���B�����ł���A�}���N�X�́u���{��`�v�̐��ŁA����������u�s��o�ρv�̐��Ő��Y�͂�����I�ɑ��傷��Ƃ������Ƃ�F�߂Ă������ƂɂȂ�B�u�o�ϊw�v�ɑ������}���N�X�Ȃ�A����͔F�����Ă��Ă����������Ȃ��ł��낤�B �@�s��o�ό�����������R�����������Ƃ������Y�̐����~�ꂵ���u���Y��`�v�̐��ł́A���������Đ��Y�͂������邱�Ƃ��炢�A�Ƃ��̐̂ɕ������Ă����̂ł��낤�B�������}���N�X�́A���O�_�Ƃ��ẮA�u���Y��`�v�o�ϑ̐��Ŗ����ɖL���ɂȂ�Ƃ����Î��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@���Ƃ��Ɓu���{��`�v�Ƃ������̂̓}���N�X�����݂Ƃ��đn���������̂ŁA���݂�����̂ł͂Ȃ��B���R�������Y�̐����B��̌o�ϑ̐��ł���B�������Љ�ƂČ����͓����ł���A�����̈قȂ���̂ł͂��蓾�Ȃ��B�u���{��`�v�͔ے�̂��߂̔ے�ޗ��Ƃ��Đݒ肳�ꂽ���̂ɂ����Ȃ��B���Y��`�̈����Ė��Ƃ��ēo�ꂳ����ꂽ���̂ɂ����Ȃ��B �@�����ł悭�����Ƃ��炵���_�c����鎑�{��`�ƎЉ��`�A���邢�͋��Y��`�Ƃ̎��ʐ��͉ˋ�̂��̂ƂȂ炴��Ȃ��B�������������̐��i����ߑ㉻������̎��ʌ��ۂƌ��A�����X�G�[�f��������̕������Ƃ����{��`����̎��ʌ��ۂ̃T���v���ƍl���邪�@���͈Ӗ����Ȃ��Ȃ����ƂɂȂ�B �������{��`�͎�i�ł���A�o�ϑ̐��ł͂Ȃ� �@��܂��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�u���{��`�v�Ƃ������t�ł���B����͍����Ɍ��炸�A�����̐l�X�̊Ԃɂ���ʉ�����Ă��邪�@���ł���B���̈Ӗ��̂Ƃ���͋��ʂ��āA�Љ�Ȋw�̗p��Ƃ��āA�܂�o�ϑ̐��̈�Ƃ��Ď���Ă��邱�Ƃł���B���������v�l�p�^�[������͓��R�̂��ƂȂ���A���Y��`�A�Љ��`�A���邢�͕�����`�Љ�Ƃ��������̂��Ή����Ƃ��đΔ䂳���̂���Ƃ���B �@����͂Ƃ�ł��Ȃ����ł���B���_���l�����́u���{��`�v�Ƃ������t���Ӗ�����Ƃ��́A��i�A���@�Ƃ��čl���Ă�����̂ł���B�����_���l�ɐ�`����Ƃ��́A�}���N�X��`�ɂ���@���Љ�Ȋw�p��Ƃ��Ĉ�̂���ߓn���̌o�ϑ̐��Ƃ��Ĕ��荞��ł���̂ł���B��������傫�ȍ�������������Ă���͓̂��R�ł��낤�B �@���_���l�́A���{��`�Ƌ��Y��`�𗼌��Ď�`�Ƃ����Ă���̂ł���B����ȊO�͂��̗����Ď�`�̈������Ė��ɂ����Ȃ��B�������Љ�A�Ñ�z�ꐧ�Љ�A���n���Y���Љ����������_���l�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł������̂ł���B ���Y��`�����}���N�X�������Y�}�錾 ���{��`�������[�j�������鍑��`�_ �@���̂Q�𗼌��ĂƂ��Ď���ړI�̒B���Ɍ������Ƃ������Ƃł���B �@���Y��`�͊v���Ƃ�����������̍��ƕ���A���͒D���ڂ������̂ł���A�P�X���I�ɂ͂�����啐��ƍl���Ă����̂ł������B������ɁA�Q�O���I�ɓ���Ɓu���{��`�v�������ɔ��B���v��ʃ`�����X������ƃ��_���l�B�͍l����悤�ɂȂ����̂ł���B����́g�푈�h�ł���B���[�j���̂����@���u�푈�͊v���ւ̍ŒZ�����ɂ���܂��ƂȂ��`�����X�ł���v�B�����ă��[�j���̓z�u�\���́u�鍑��`�v���ێʂ��ɂ��ĊO�ς��A����Ƃ��Ắu�鍑��`�푈�s��_�v������_�̂��̗L���ȁu�鍑��`�_�v�������グ���̂ł���B �@����͐���̂��߂̋��\���݂ł���B���[�j���̗p�������@�̓}���N�X�Ɠ����ُؖ@�I�B���_�Ƃ������\�ł����Čo�ϓI�v�������ׂĂ�������Ƌ��ق��邱�Ƃɂ��A�푈�K�R�_�̕����ւ����Ă������Ƃ���킯�ł���B���[�j���ɂƂ��ẮA�푈���N�����Ȃ����{��`�Ȃ��O���̒l�ł����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�܂�u���{��`�v�u�鍑��`�v�Ƃ������̂͊v���̏��a����푈���N�������߂̎�i�A���@�ɂ����Ȃ��̂ł���B �@�����ŗႦ�A�u�s��o�ό����v�Ƃ������t�ŕ\�����Ă͂ǂ����B���ɂ����낢�날�낤�B�u�s��o�ϑ̐��v�u���R�������Y�̐��v�Ȃǂ�����悤�����A������ɂ���A�Љ�̌o�ϑ̐��Ƃ������͎̂��R������B��̌����Ƃ�����̂ł���B���������ėႦ�Γ��{�ł����A�]�ˎ���������Ȍ���S�������o�ϑ̐��ɑ��Ȃ�Ȃ��B�o�σ��J�j�Y���̕��G���A���Y�́A�Z�p�̍��A��Y�Ƃ̈Ⴂ�͂���A�]�ˎ���������ȍ~���������R�����������Ƃ������Y�̐��ł���B �@���R�����o�ϑ̐��Ƃ����ςȌ��t���A���Y��`�Ƃ����a�O�`�Ԃ̌o�ϑ̐����}���N�X���n���������߂ɂ��̑Ή����Ƃ��āA�܂������̌o�ϑ̐��̈�ł��邩�̔@�������o�����悤�ɂȂ����B���R�̐ۗ��Ƃ��ĕ����Ƃ������̂͌����Ă��蓾�Ȃ��B�o�ςɂ����Ă����R���������R�̐ۗ��ł���B �������ʘ_�̃i���Z���X �@�u���{��`�v�u�Љ��`�v���o�ϑ̐��ƌ�F���邱�Ƃ����S�̌��ʂƂ��Ď��ʘ_�Ƃ������̂܂ŏo�Ă��Ă���B���{��`�ƎЉ��`�����ʂ��邩�̔@�����z������̂����\�_���ɂ͂܂��Ă��܂��ނ��뎩�R�����m��Ȃ��B �@�������悭�l���Ă݂�A����́u���R�ƕ����̎��ʁv�Ƃ��������ނ̊T�O�Ɏ��ʂ���邱�ƂɂȂ�B���R�ƕ����͌����ė������Ȃ��B���̓_����l���Ă��u���{��`�v�u�Љ��`�v���o�ϑ̐��ƍl���邱�Ƃ̌��͗��ł���̂ł͂Ȃ����B �@���_�������́A����ړI�̂��߂Ɏ��Ȃ̃��V�A�v�z����Ƃ��āu���Y��`�v�Ƃ����ˋ�̂��̂�n�����A�����ł͎��R�����������Ƃ����u���{��`�v�������̍������鈫�ʂɎd�グ����`�������킯�ł���B �@�f�B�A�X�|���ȗ��̕M��ɂ�������������E���邽�߂ɂ́A������Έ��Ƃ����̑Ή����Ƃ��Đ�ΑP�̉ˋ�̖�����ݒ肷��Ƃ����l���́A�������R�̂��̂ł���B������A�@�������ł���Ȃ�����Ƃ����悤�B���̌���̐�Έ����u���{��`�v�Ɩ��������܂łł���B �@����A��ΑP�̉ˋ�̖������u���Y��`�v�Ƃ���킯�ł���B���_�����̎����͂̑傫�������߂ĒɊ���������̂́A�����̔@���P���ɂ܂�Ȃ��_�b���ߐ��j�ɂ������傫�ȉe�����y�ڂ��l�ނ̗��j����H�ɒǂ����Ƃ��������ł���B���ݐ��E�̂R���̂P���߂鍑�X�ł́A���R�����̐����痣�E���Ă��܂��Ă���B�����Č��݂̃\�A�͒��R����`����������悢�拭�����Ă���B �q�����r �@ �����^�^�[���v���͔������Ȃ��\�A �@�����m�̂悤�Ƀ\�A�͔��������V�A�l�ł���A��̔����͂U�O��ވȏ�̑��������琬���Ă��鍑�ł���B�P�X�P�V�N�̃N�[�f�^�[�ŁA���_���l�̓c�@�[�̖\���ɏI�~����ł̂ɐ��������̂ł��邪�A���̌�͕s���̂��߃X�^�[�����P�l�Ƀ��_�����͂͂Ԃ���Ă��܂����B���̌����͂��낢�날�邪�A�ԌR�������ł��Ȃ��������Ƃ��ő�̔s�����Ǝv���B���̂Ȃ�A��X���_���l�͌R�l�Ƃ��Ă̑f���͋ɂ߂Ďキ�A���ꂪ�ԌR������s�\�ɂ��������Ǝv����B �@�X�^�[��������͏��X�Ƀ��V�A�l�̌��͂������Ȃ�A�����ł̓��V�A�l�łȂ��Ă͎w���I�|�X�g�ɂ����Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�����\�N���A�V�A�l�i���̂��Ƃ��\�A�ł̓^�^�[���Ƃ����Ă���j�A�܂�^�^�[���͑��ꂵ����C�̒��ň����ׂ��ꂽ�悤�ɂȂ��Ă���B���w���̐���������A�@���Ȃ�l�����w���������邩�A���ꂾ���͑S���\�������Ȃ����A�W�O�N��ɂ͌o�ϓI�ȓ����d���ǂƂ����킹�ă^�^�[���l�̓����͊�����������Ȃ����낤�B�\�A�����݂̑a�O�`�Ԃ̍��Ƃ���������̂́A�o�ϓI�s�����q�ł͂Ȃ������I�s�����q�ł���B �y���a�ȎЉ��]�ނȂ��z �@�y�u�Ⴆ�v�̑z���z |